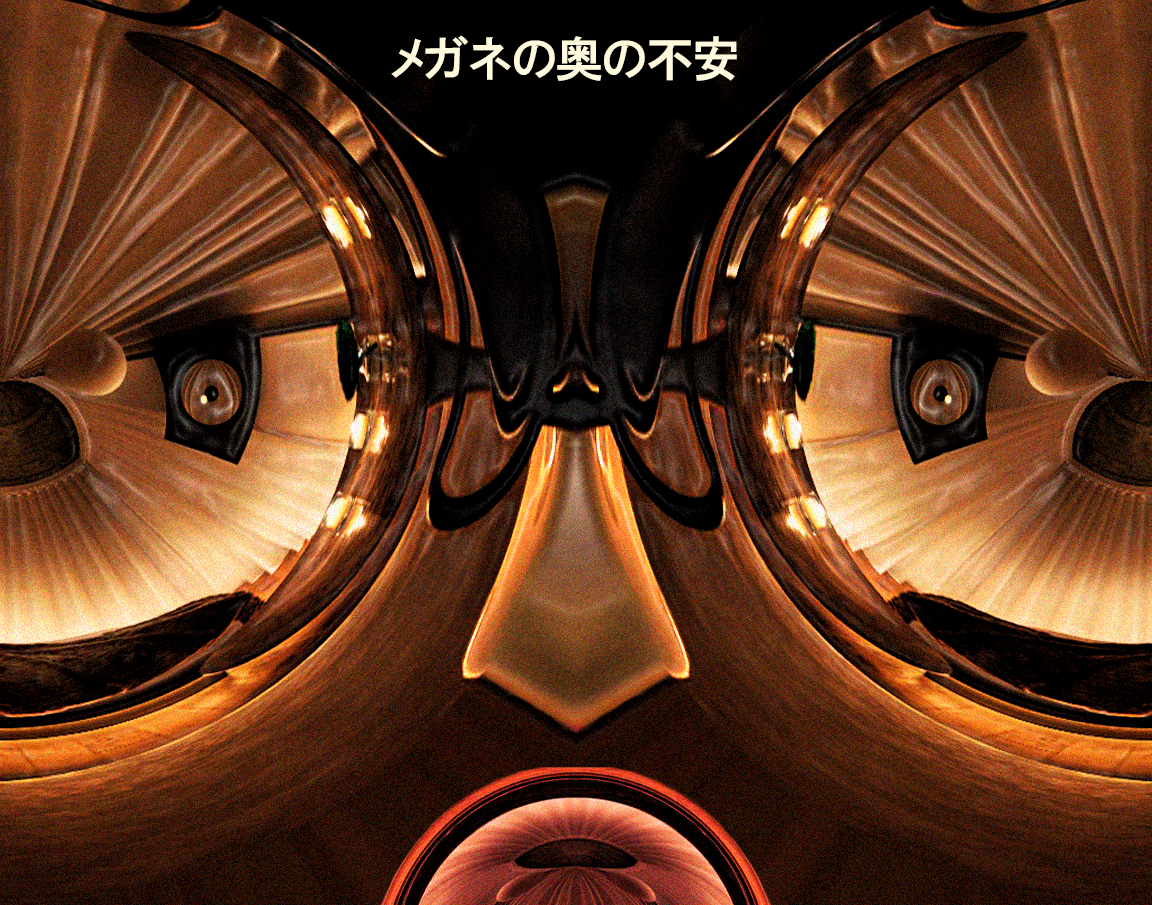Title : 火露美(ひろみ)

Title : パチンコ丸シロー
竹垣の下、シローは身体をペッタンコにして、手入れされぬまま繁り放題の庭樹と雑草の隙間をムリムリ通過、存在を消しながら庭内の様子を探る。
10畳ほどの庭。正面に縁側。先ほどまで訪問していた医者か看護婦が全開にしたに違いない古びた左右障子(しょうじ)戸。
こちら側を頭にフトンに横たわるのは白髪のオバアチャンか?。
たぶん飼い主だろう…。その顔を覗き込むようにキチンとお座りしたシロー憧れの初恋相手、ヒロミ(火露美)。
小枝に触れて音が立たぬよう、シローは最新の注意を払いながら窮屈な姿勢を立て直し、ゆっくりと繁みに四つん這い姿勢で座す。
「ヒロミ、見たか。柿の実がずいぶんと熟した色になってきたろう?。青いのも多いけどなぁ…。今年は食べられんで終わってしまうかもしれんから、さみしいよぅ……」
か細い声で飼い猫に話しかける女性。シローは右手の柿木に目をやった。3m丈の木は、たわわに実った柿を身にまとい秋化粧。それらはザッと観たところ、濃いオレンジ色一色のものと未だ半分青色のものがせめぎ合っている状態だ。
再び縁側に目を向けると、ヒロミが飼い主の声を聞きとろうと顔を白髪頭に近づけたところ。
「お前はこれを食べなね。アタシが開けてやるから今ね」
枕元の猫缶を仰向けの胸の上に乗せフタを開けようとする飼い主。薄地の浴衣の袖が落ち、やせ衰えた浅黒い両腕が見えた。
一生懸命に力を込めてフタを開けようとしている飼い主の焦りがシローにもハッキリと伝わって来る。
十分も経った頃だろうか。辛抱強く、身じろぎひとつせず座していたヒロミが半身を伸ばし、飼い主の左腕をふいにペロペロと二度舐めた。その瞬間、シローの聞き覚えのあるパカッという音が聞こえ、奇跡的にフタが開いた。
「ああ、ああ、開いた、開いた、良かった良かった、ほらほら、食べなさい」
隙間風のような笑い声が聞こえ、飼い主は半身を懸命にネコに向けようとあがき、ようやく缶詰をヒロミの足元に置くことに成功した。
ネコ缶に鼻先を入れ、おとなしく食べ始めるヒロミ。シローは首を長ぁく伸ばしネコ缶の銘柄を確認しようと試みる。見慣れたブルー地にピンク文字。
“ オレの安物並缶と同じだないか!”
上流階級イメージのあるヒロミさんが自分と同じ並缶を食べているとは意外だ。シローは食い入るように縁側の光景に目をこらす。
その時だ、何故か無意味に踏ん張っている後ろ足左の肉球にチクリと痛みが走った。
“ アッ!キショーめ!アリだなッ!! ”
普段なら、こんな場所に絶対長居などしないのだが。音を立てられないのでアリを憎々し気に叩くこともままならない。
気を取り直し、再び縁側に視線を戻す。ゆっくり、品よく食べ続けている飼い猫の背中を飼い主が撫でている。その左腕が突如パタリと畳上に落ちた。
一瞬、二匹の猫の心臓が止まった。
そして再び鼓動が再開される。
二匹の猫は微動だに動かない。二匹の周辺の時間は完全に静止状態にある。
そして再び時間が動き始めた。
ユックリと立ち上がり、何かを追うように、導かれてでもいるかのように、ヒロミは空中の一点を目で追いながら縁側に出てゆく。
シローの真正面にヒロミの顔がある。だがシローは隠れようともせずヒロミと同じ宙の一点に目をクギ付け、身じろぎもしない。
二匹のネコの顔はさらに一層上を向く。その視線の先にあるのは柿の木の枝。
最初、柿の木の枝先の完熟した柿の実が、無風の中、大きくゆっくりと揺れた。一拍あってその上の枝の柿の実。同じく熟した実だけが大きく揺れる。
二匹のネコは立ち上がり首を精一杯伸ばして空を見上げる。
雲一つない一面の青空に何かが吸いこまれ、余韻も痕跡も残さず
消えた。
再び、時間が止まり、二匹のネコは石像のように動かなくなった。
どれほどの時が流れたのだろう。1分かもしれなかったし、1時間かもしれなかった。
魔法がほどけたかのように、ヒロミがゆっくり部屋に戻り始めた。薄暗くなり始めた和室の畳に座し、食事の続きを始めた。ゆっくり、とてもゆっくり、ひと味ひと味を噛みしめるかのように。
アジを手に大騒ぎしながらはしゃいでいる信号待ちのネコ達の後ろを早足で抜け家路を急ぐシロー。
途中、出がけに見かけた小娘ネコと目が合った。彼女が重そうに両手で下げたバスキャップの中はたくさんのアジで満たされている。小娘は、小麦粉まみれで開かない片目ではない方の目で笑うと、さも嬉しそうにみゃあ~♪とひと声鳴いた。
シローは何の反応も返さずただ黙々と家路をたどる。その途中途中、行く先、行く先、まるで水先案内でもするかのように人家の灯りが次々にともってゆく。
「アレ?!、シロー、ザルは?!。どした、アジはどしたの」
待ちかねていたオミヤがキッチンに現れたシローの姿を見て驚きの声を上げ、その顔は飼い猫の暗い面持ちにみるみる曇ってゆく。
「シロー………。アジは……」
「取れんかった。お腹空いとるのでネコ缶出してくれんか」
「何で名人のお前が取れなかったのかね…。アタシがプレミアム猫缶を今から買ってきてあげっからさー、ちょっと待ってなよ~、ねぇ~?」エプロンをほどき出かけようとするオミヤ。
「並缶が食べたいのだから」
普段とあまりに違う飼い猫の重く暗い声に、こちらに背を向けTVを見ていたパピーとマミーが思わず振り返る。
シローはネコ缶のフタを取ってもらうと、それを二階の自室に持って行くようオミヤに頼んだ。
「何か様子が変じゃない?。オバアチャン、何か聞いた?」とマミー。
「便秘だからアジ取るの気が進まなかったんだよ、きっと。こっちも夕飯にしようよ」とパピー。
暗い部屋。明かりもつけずネコ缶を食べるシロー。ゆっくり、ゆっくり、噛みしめる様に食べている。
人は泣いて想いを外へ吐き出す。ネコは涙を流せない。思いは、いつまでもいつまでも胸の中から吐き出されることがない。
そのことが、
これを書いているボクを泣かせる。