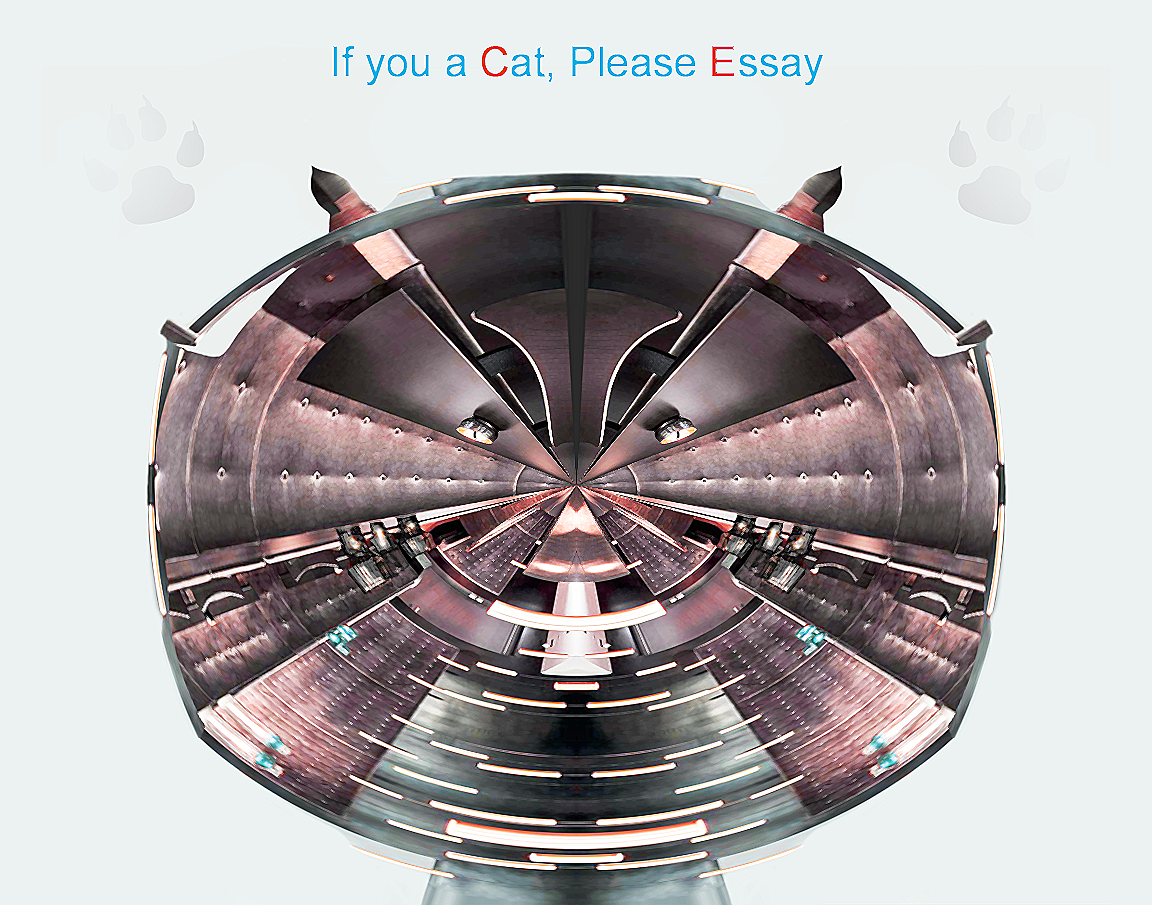君知るや草のささやき
ボクは菓子パン3個が入ったビニール袋を時折太陽にかざしてパンの影を眺め楽しんでいたが、さすがにそれも飽きた。興奮冷めやらぬ逆上がりの奇跡から1日、ボクは名も知らぬ彼を校庭鉄棒前で待つ。
もしかしたら再び彼が現れるかもしれない、と昨日より1時間程早めに此処へ来た。来てすぐに見事な逆上がりを連続3回決め、周囲の山々眺め回して余裕の高笑い。
パンは2個を彼に、1個をボクに。昨日言い忘れたお礼を言った後に2人で並んで食べる。
クリームパン2個にアンドーナツ1個。ボクはアンドーナツが狂おしい程食べたかったものの、それは彼に進呈することに決めていた。
それはクリームパンより40円も高い。これこそが彼への誠意というものだ。手持ちのお小遣いさえあればボクにもアンドーナツが………、アッ!
向こうからやって来る彼が手を振っている。ボクも慌てて手を振り返す。立ち上がりざま妙な気恥ずかしさでベロを強く噛んでしまった。
いでぃぇぇ…。
嬉しそうに微笑みながら「どうしたの。逆上がりの練習?」
「うん。……ああ、これ昨日のお礼」
反射的に袋ごと手渡してしまい顔面からサッと血の気が引く。彼は覗き込むと、ちょっと驚いた顔で「いいの?」「うん。少ないけど」
彼は誰も居ない校庭が好きで、休みの日はよく山道散歩の途中で校庭に立ち寄ることが多いと言った。「一緒に散歩する?」「うん」
誘われるままボクは彼と山道に入った。昼間の山道はボクも良く知っている。
最初は緊張で頬がひきつっていたボクも、コレがカブトムシがよくいるクヌギの木だとか、この倒木によくタマムシがいるだとか、自分の秘密を洗いざらいゲロするうち、激しく饒舌になっていった。
彼はニコニコしながらボクの話を興味深く聞き、時折指摘される木々を覗き込んでは軽く頷いてみせる。
「ここ(坂道)を降りたらすぐオレんち、ちょっと来る?」「うん」
これまで山の反対側には言ったことがなかったので、彼の家がここいらに在るというのにはヒドく納得。
林の奥まった目立たない場所に彼の家はあった。隠されている様な印象もあったが、一階建ての非常にオンボロ木造の前、庭と呼ぶにはふさわしくなく、つまらない空き地と呼ぶが似つかわしい、漠然とした広場があった。
敷地らしきこの場所に柵はなく、代わりにグルリと雑木林が一帯を取り囲んでいる。コンビニ一店舗分の広場の真ん中には使いこまれた真っ黒なドラム缶が置いてあり、傍らには石鹸の入った金タライと擦り切れたタオルが無造作に置かれていた。
「これがウチの風呂なんだ」と言って彼は笑い、家から飛び出してきたちっちゃな女の子を見るや、スタスタ近寄ってパンの入った袋を手渡し「1つ好きなの食べていいよ」。やさしい声がかすかに聞こえボクを動揺させる。アンドーナツを選ぶのだろうか…。
彼はドラム缶から1メートルほど離れた焚火跡の黒焦げ枝を手で軽く押しのけ、あったあった、と嬉しそうに笑うと、真っ黒な塊を取り上げ両手でゴシゴシ黒焦げを削り落とし、ハイ、と言ってボクにそれを手渡した。
よくよく見ると細っこい焼き芋!。オオ!。ボクの驚きで焼き芋が激しく上下するさまを見て彼はさも可笑しそうに、あっはっはっは!と笑った。黄金色に光輝く芋の身を少しずつほぐし食べるボク。芳醇な甘く冷たい味覚がボクをたちまち虜にする。何て幸せな…そこへ彼の父が帰宅。
まっすぐこっちへ向かって歩いて来る。真っ黒に日焼けした顔からボクに向かって真っ白な歯がご挨拶。なるほど親子、ソックリだ。
「今からヘビ取り行くから手伝ってくれ」「ああ、いいよ」
父は家へと戻って行った。「ヘビ?」「うん。一緒に行く?」
訳が分からぬまま同行する。日は傾き始めている。夕暮れから日没直前に捕獲するという。「うちのトウチャン、ヘビ獲って売るのが商売だから」
嗚呼。あの日の事ことは、どうにもこうにも忘れられない。何故かすぐに見つかるヘビ。毒のないシマヘビの首にシャッ!と目にも留まらぬ早業で棒先の首絞め紐がヘビの首を絞める!。
父親が棒で弧を描くと、のたうつヘビは息子が待ちかまえている麻の大袋大口へと鮮やかに落下!。ヘビの首から紐輪が素早く抜かれると同時、息子が麻袋の口を閉めて直ちに麻紐がけ!。
呆然自失のボクの目の前、のたうつヘビの姿が何度も行き来、ヘビのウロコがなまめかしく光るさまを見せつけてはシッポピラピラ、また明日。それは妖しい黒紫の夕闇が迫りくるまで続いた。
「10匹獲れたねトウチャン!。ほら触ってみて、ヘビ動いてるよ」
輝く笑顔でボクに向き直る彼。言われたビビリは、彼が掲げ持つ年期の入った麻袋を両手の平でポンポンと触ってみる。何ともいえぬヘビの這いまわる感触に髪の毛は逆立ち、ショックのあまり失神寸前。
不思議に名乗りあわず、その日以降、ボクと彼は一度も顔を合わせていない。嫌いになったわけではない。彼への親しみと懐かしさは今なお色褪せる事はない。ボクらは知っていた。お互いの住む世界が違うのだということを…。学校で顔を合わせなかったのか?。
どの小学校にも、彼に在籍の記録はなかった。